西尾幹二といえばニーチェの研究家であり、ドイツ哲学書の翻訳家である。少なくともわれわれの世代にはそのような印象が強い。しかし最近はナショナリストとしての言動が目立つ。「新しい歴史教科書をつくる会」を1996年に立ち上げた西尾が著した本書は、しかしいわゆる歴史教科書ではなく、一般常識として浸透している「日本の歴史」概念を批判する個人的評論となっている。 西尾はまず古代日本が中国から絶大な影響を受けたという通説に異議を唱える。なるほど日本は中国から漢字を輸入したが、それはあくまでも文字レベルの話である。 紀元前一世紀後半あるいは紀元後二世紀に漢字との接触が始まってから、日本が漢字を自分のものにするまでに約一千年という長い歳月をかけていることに西尾は注目する。日本語の中の漢語の量が増加するのは平安時代になってからで、『万葉集』では0.3%だったのが『伊勢物語』で全体の6.2%、『枕草子』になると13.8%が漢語である。平安時代に20%にまで増加し、鎌倉時代には約25%、室町時代には約30%、江戸時代には約35%が漢語で、現代では約45%に達しているという。時代が新しくなるにつれて漢語が減るのではなく、逆に増えているというのが面白い。 西尾は言う。現代のわれわれには文字によって書き残された資料を介してしか歴史を知ることができないが、文字の使用以前に日本には日本独自のオリジナルな文化があったのではないか。その文化が漢字の流入を意識的に拒否していたのではないか。表意文字である漢字のみでは語と語の関係を表現することができず、また読み方が地域によって異なるため口頭での広範囲への伝達が難しいという欠点もある。日本の文化が成熟し完成してようやく、漢字を自在に利用する余裕を手に入れたのではないか。「文字は言語に及ばない、言語は行為に及ばない」という西尾の主張は、『ニーチェとの対話』における「言葉は行為の影に過ぎない」という主張とも共通しており興味深い。 決定版 国民の歴史〈上〉 (文春文庫) 関連情報
 GHQ焚書図書開封1: 米占領軍に消された戦前の日本 (徳間文庫カレッジ に 1-1)
GHQ焚書図書開封1: 米占領軍に消された戦前の日本 (徳間文庫カレッジ に 1-1)
長年、入手が困難な本でした。まさか新刊の出版に感謝。出来れば文庫本でなく単行本であって欲しかったです。(図書館で閲覧出来ると良いので)心ある方々にも回覧したい本です。 GHQ焚書図書開封1: 米占領軍に消された戦前の日本 (徳間文庫カレッジ に 1-1) 関連情報
当シリーズでも、一般に常識とされてきた(させられてきた)ものを次々と覆してきた、西欧を知りぬく筆者が繰り出す相変わらずの超弩級の問題提起です。西欧とは?近代とは?そして日本とは?歴史で「思わされてきた」「考えされられてきた」こと。そして、当時読み解けても、、また当時すらも読み解けなかったこと。GHQにより過去のものとされた水戸学の「知られざる」苦闘を通して西欧を知りぬく知識人西尾幹二が超弩級の問題提起を繰り出します。たとえば、ここに取り上げられた水戸学の先覚よりも評者は、外国語も数か国語もはるかにでき、外国の情報もネットで素早く取れ、それを読み解く背景の知識もあるはず、、、です。しかし、当時の知性はどう捉え、応じたのか。これを筆者は当時のリアルな認識の根源を次々に明らかにしていきます。現代が如何に外国の借り物のそして借らされものの知識や情報に、そして戦後のGHQの優等生的歴史観に踊らされているだけなのか、「水戸学」を通して、明らかにしていく過程を読んでほしいと思います。特に後半の山本七平批判は評者も年来思っていた、うまく言葉にできなかったモヤモヤ、が、やっと取れた思いがしました。 GHQ焚書図書開封11: 維新の源流としての水戸学 関連情報



![AKIRA YAMAOKA - YOSHIDASAN (ヨシダさん) [720p] 吉田依存症](http://img.youtube.com/vi/uD_8PglDEw8/2.jpg)


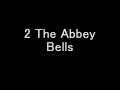


![Red Hot Chili Peppers - Californication [Official Music Video] サフォケイション](http://img.youtube.com/vi/YlUKcNNmywk/1.jpg)




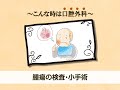











![デジタルカメラマガジン 2015年10月号[雑誌] デジタルカメラマガジン 2015年10月号[雑誌]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B015FB6I1S.09.MZZZZZZZ.jpg)